「高校受験 地理 覚えること まとめ」…このキーワードで検索したあなたは、きっと地理の勉強法に悩んでいたり、もっと効率よく得点アップしたいと考えているのではないでしょうか?
大丈夫! この記事は、まさにそんなあなたのために書かれました。高校受験の地理って、覚えることがたくさんあって大変…そう思われがちですが、実は、ポイントを押さえて効率よく学習すれば、確実に得点源にできる科目なんです!
この記事では、高校受験地理で「覚えること」を徹底的にまとめ、さらに、成績アップに直結する勉強法まで、余すところなく解説していきます。「何から手をつければいいか分からない…」「地理の勉強はつまらない…」そんな悩みも、この記事を読めばきっと解決するはず!
さあ、私たちと一緒に、地理の攻略法をマスターして、志望校合格への扉を開きましょう!
- 高校受験地理で覚えるべき最重要ポイントが、基礎から応用まで網羅的に分かる。
- 地図、グラフ、統計データなど、地理特有の問題の解き方が具体的に理解できる。
- 効率的な暗記法や、他教科との関連学習など、地理の成績を伸ばすための勉強法が身につく。
- 時事問題対策や、よくある疑問への回答など、高校受験地理で差をつけるための知識が得られる。
高校受験地理覚えることまとめ【基礎編】
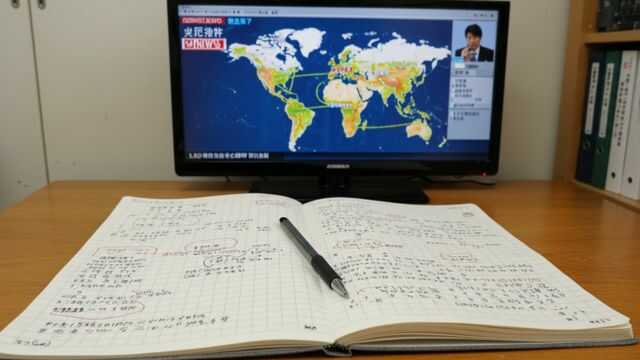
中学地理要点まとめ:世界
地理を覚えるのって大変そうに感じるけど、イメージを膨らませると楽しくなるよ!“世界を旅する気分”で学んでみよう!
世界の地理を学ぶのって、まるで宝探しみたいでワクワクしませんか? まずは、地球儀をぐるっと回して、大きな大陸と海の名前を覚えちゃいましょう! 六大陸(ユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸)と三大洋(太平洋、大西洋、インド洋)は、地図帳で場所を確認しながら、声に出して覚えるのがおすすめです。「ユーラシア大陸って、アジアとヨーロッパを合わせた、めっちゃ広い大陸なんだ!」とか、「太平洋って、日本の目の前に広がってる、あの広い海のことか!」みたいに、自分なりの言葉でイメージすると、頭に入りやすいですよ。
次は、主要な国の位置と首都を攻略! 特に、面積が大きい国(ロシア、カナダ、アメリカ、中国、ブラジル…)や、人口が多い国(中国、インド、アメリカ、インドネシア、パキスタン…)は、要チェック。ニュースでよく聞く国も多いですよね。
ニュースで聞いたことのある国や地域が出てきたらチャンス!実際の出来事と結びつけると、記憶に残りやすいよ。
「ロシアって、めちゃくちゃ寒い国っていうイメージだけど、実は世界で一番広いんだ!」とか、「中国って、人口も多いけど、経済もすごい勢いで成長してるんだって!」みたいに、国の特徴とセットで覚えると、忘れにくくなります。
さらに、世界の気候帯も知っておくと、世界旅行がもっと楽しくなるかも! 熱帯、乾燥帯、温帯、冷帯(亜寒帯)、寒帯の5つの気候帯、それぞれどんな特徴があるか、想像できますか? 例えば、熱帯はジャングルみたいなイメージ、乾燥帯は砂漠、温帯は日本みたいに四季がある…みたいに、自分の知っていることと結びつけると、覚えやすいですよ。雨温図を見て、「この気候は…あの国っぽい!」ってピンとくるようになったら、もう地理マスターに一歩近づいた証拠!
練習問題:
- 三大洋、全部言えるかな?
- 面積が世界で2番目に大きい国はどこでしょう?
- 熱帯雨林気候って、どんな感じ? 自分の言葉で説明してみて!
中学地理要点まとめ:日本
日本の地理は、私たちの住んでいる国のことだから、もっと身近に感じられるはず! まずは、47都道府県の位置と県庁所在地をバッチリ覚えましょう。パズルみたいに、地方ごとに分けて覚えるのがおすすめです。「関東地方って、東京以外に何県があるんだっけ…?」とか、「東北地方って、雪がたくさん降るイメージだけど…」みたいに、クイズ形式で友達と出し合うのも楽しいですよ。白地図に書き込む練習も、ゲーム感覚でやってみましょう!
次に、日本の地形をじっくり観察! 日本って、山が多くて、平野が少ないって知ってましたか? 主な山脈(日本アルプスとか、奥羽山脈とか…)、平野(関東平野とか、濃尾平野とか…)、河川(信濃川とか、利根川とか…)、湖(琵琶湖とか、霞ヶ浦とか…)の名前と場所を、地図帳で確認! 「日本アルプスって、”日本の屋根”って呼ばれてるんだ!」「関東平野って、こんなに広いんだから、そりゃあ人もたくさん住むよね~」みたいに、理由と一緒に覚えると、記憶に残りやすくなります。
そして、日本の気候。四季があるのは当たり前だけど、地域によって全然違うって知ってました? 日本海側は冬に雪がたくさん降って、太平洋側は夏に雨が多い…。梅雨や台風も、日本の気候の大事なポイント。「日本海側って、雪まつりが有名だけど、雪かき大変そう…」「太平洋側は、夏に台風が来るから、気をつけないと…」みたいに、自分の生活と結びつけて考えると、より理解が深まります。
さらに、日本の主要な産業についても触れておきましょう。車を作ったり、電子部品を作ったり…日本って、実はすごい技術を持った国なんです。農業では、お米はもちろん、地域によって色々な野菜や果物が作られています。漁業も盛んで、美味しい魚がたくさん獲れるんですよ! これらの産業が、どの地域で盛んなのか、地図帳でチェックしてみてくださいね。
練習問題:
- 日本の都道府県、いくつ言える?
- 日本で一番長い川って、どこにあるか知ってる?
- 日本海側の気候の特徴、説明できる?
高校受験地理生産量:統計データ
地理のテストって、数字がたくさん出てきて、ちょっと苦手…って人もいるかもしれません。
地理の暗記が苦手で、なかなか覚えられません。どうしたら効率よく覚えられますか?
地理は“意味とセットで覚える”ことが大切!例えば、『中国は人口が多い』→『だからお米の生産量も多い』みたいに、理由を考えると記憶に残りやすいよ。また、白地図に書き込んだり、クイズ形式で友達と問題を出し合ったりするのも効果的。楽しみながら学ぶことが、記憶定着のコツだよ!
でも、農産物や鉱産資源の生産量のデータは、世界の国々のことを知るための、とっても面白いヒントになるんです!
例えば、お米。どこの国がたくさん作っていると思いますか? 中国、インド、インドネシア…これらの国は、人口も多いですよね。つまり、「たくさんの人が食べるから、たくさん作っている」ってこと。小麦は? 中国、インド、ロシア、アメリカ…。「ロシアって、寒いイメージだけど、小麦も作ってるんだ!」って、新しい発見があるかも。とうもろこしは? アメリカ、中国、ブラジル…。「アメリカって、広い土地で、色々なものを作ってるんだな~」って、感心しちゃうかも。
これらのデータは、丸暗記するよりも、**「なぜその国でたくさん作られているのか」**を考えることが大切。「アメリカは、広い土地と、進んだ農業技術があるから、とうもろこしがたくさん作れるんだ!」みたいに、理由とセットで覚えると、忘れにくくなります。
最新のデータは、インターネットで「○○(農産物名) 生産量 ランキング」みたいに検索すれば、すぐに見つかりますよ!
練習問題:
- 2023年のデータで、小麦の生産量が世界一の国、どこだっけ?
- 石油がたくさん取れる国、3つ挙げてみて!
- なんでその国で、その農産物がたくさん作られているのか、理由を説明できる?
一問一答で力試し!
地理の勉強って、覚えることがたくさんあって大変…って思うかもしれないけど、一問一答形式の問題で、ゲーム感覚で楽しく復習しちゃいましょう! 一問一答は、短い時間でたくさんの問題にチャレンジできるから、スキマ時間にもピッタリ。
例えば…
- 「日本の最北端の島は?」(択捉島!)
- 「アフリカ大陸で一番大きい国は?」(アルジェリア!)
- 「アンデス山脈って、どの大陸にあるんだっけ?」(南アメリカ大陸!)
- 「日本の時間を決める大事な線、東経何度?」(135度!)
…みたいに、友達とクイズを出し合うのも楽しいですよ!
間違えた問題は、落ち込む必要なし!
間違えるのは成長のチャンス!クイズ感覚で何度も挑戦して、楽しく覚えていこう!
むしろ、「ラッキー! 新しいことを覚えるチャンス!」って思っちゃいましょう。間違えた問題だけをノートにまとめたり、付箋に書いて、目につくところに貼っておくのもおすすめです。
練習問題:(上の例文はもう使っちゃったから、別の問題ね!)
- 世界で一番高い山、名前は?
- 日本で2番目に大きい湖はどこにある?
- オーストラリアの首都、言えるかな?
図表で理解!よく出る問題
地理のテストには、地図やグラフ、表を使った問題が必ず出てきます。これは、ただ知識を覚えるだけじゃなくて、**「情報を読み取る力」**も試されているんです。でも、大丈夫! コツさえつかめば、絶対に解けるようになります!
例えば、雨温図。これは、気温と降水量をグラフにしたものだけど、これを見れば、その場所がどんな気候なのか、一目でわかるんです。「このグラフ、雨が少なくて、気温が高いから…砂漠っぽい!」みたいに、推理ゲームみたいで、ちょっと面白くないですか?
統計グラフも、同じ。グラフのタイトル、縦軸と横軸の単位、凡例をしっかりチェック! これらの情報から、「このグラフは何を表しているのか」「何が一番多いのか」「どんな変化があるのか」を読み取る練習をしましょう。
普段から、地図帳や資料集をパラパラめくって、色々な図表に慣れておくのがおすすめです。過去問を解いて、「こういう問題が出るんだ!」って、パターンを知っておくのも、テスト対策には効果的ですよ。
高校受験地理覚えることまとめ【応用編】
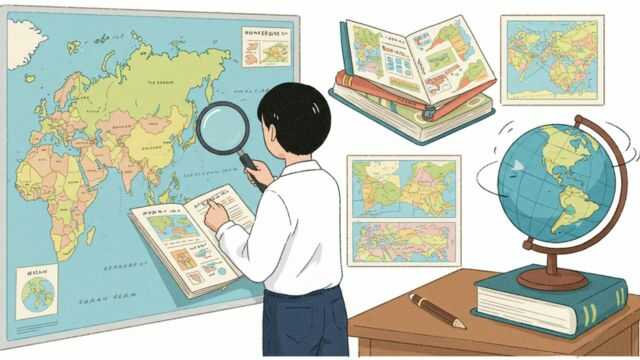
時差問題マスター!計算攻略
時差の問題って、なんだか難しそう…って思うかもしれないけど、大丈夫! 時計をイメージして、落ち着いて考えれば、絶対に解けるようになります!
まず、地球は、くるっと1回転(360度)するのに、24時間かかるってことを思い出して。ということは、1時間で15度(360度 ÷ 24時間 = 15度)回ってるってこと。この「1時間で15度」が、時差を考える上で、とっても大事なポイント!
次に、世界地図を思い浮かべて! イギリスのロンドンを通る線(本初子午線)が、経度0度。そこから東に行くと時間が進んで、西に行くと時間が遅くなる…って、なんとなくイメージできるかな?
例えば、東京(東経約135度)とニューヨーク(西経約75度)の時差を計算してみましょう。まず、2つの都市の経度の差を計算。135度 + 75度 = 210度。次に、この210度を、1時間あたりの15度で割ると…14時間! 東京の方が東にあるから、東京の方が14時間進んでるってことになります。
練習問題:
- ロンドンとカイロ(東経約30度)の時差、わかるかな?
- 東京が1月1日午前0時のとき、ロサンゼルス(西経約120度)は何月何日の何時? 落ち着いて考えてみて!
地形図読取:等高線を理解
地形図って、記号がいっぱいだし、線がぐちゃぐちゃだし…って、見るだけで嫌になっちゃう人もいるかもしれません。でも、等高線の読み方さえマスターすれば、地形図は、まるで宝の地図みたいに、色々な情報を教えてくれるんです!
等高線は、同じ高さの場所を結んだ線。だから、線がギュッと詰まっているところは、坂が急で、線と線の間が広いところは、なだらか~な坂ってこと。「この等高線、めっちゃ混んでる! ここ、山登り大変そう…」とか、「こっちは、線がゆったりしてるから、ハイキングに良さそう!」みたいに、地図を見ながら、実際に歩いているところを想像すると、楽しく覚えられますよ。
等高線が丸く閉じていて、内側に向かって数字が大きくなっていたら、そこは山や丘。逆に、内側に向かって数字が小さくなっていたら、谷やくぼ地。これも、地図を見て、山の形をイメージすると、覚えやすいです。
あとは、縮尺と地図記号も、大事なポイント。縮尺は、地図上の長さと、実際の長さの比率のこと。「2万5千分の1」の地図なら、地図上の1cmが、実際には250mってことになります。地図記号は、学校とか、病院とか、色々な建物を表すマーク。主な記号は、覚えておくと便利ですよ。
練習問題:
(ここでは地形図を見せられないけど、等高線、縮尺、地図記号の問題をイメージしてね!)
- この地形図の縮尺、いくつ?
- この地形図の中で、一番高い場所はどこ? 見つけられるかな?
他教科との関連をチェック
地理って、実は、他の教科とも仲良しなんです! 歴史、公民、理科…色々な教科とつながっていて、一緒に勉強すると、もっともっと面白くなるんですよ!
- 歴史: 例えば、昔の人が、どうしてこんな場所に都を作ったんだろう…? それは、川があって水が豊かだったから? それとも、山に囲まれていて、敵から守りやすかったから? …みたいに、地理的な視点から歴史を見ると、新しい発見があるかも!
- 公民: 世界には、色々な国があって、色々な政治の仕組みがあります。でも、なんでその国は、そういう仕組みを選んだんだろう…? それは、資源がたくさんあるから? それとも、色々な民族が住んでいるから? …みたいに、地理と結びつけて考えると、理解が深まります。
- 理科: 地震や火山、台風…これらの自然現象は、地球の仕組みと深く関わっています。地理では、これらの現象が、世界のどこで、どのように起こっているのかを学びます。「地震が多い国って、プレートの境目にあるんだ!」とか、「台風って、暖かい海の上で発生するんだ!」みたいに、理科で学んだ知識が、地理の理解を助けてくれることもあります。
他の教科と関連付けて勉強することで、「点」だった知識が「線」でつながって、**「なるほど! そういうことだったのか!」**って、感動する瞬間がきっとありますよ!
練習問題:
- 日本の稲作と梅雨、どんな関係があるか説明できる?
- 地理的な理由で、歴史が変わったことって、何かある?
差がつく!グラフ問題対策
グラフ問題って、数字ばっかりで、ちょっと苦手…って人もいるかもしれないけど、実は、得点アップのチャンスなんです! グラフの種類と特徴を覚えて、読み取りのコツをつかめば、怖いものなし!
よく出るグラフは、この5つ!
- 棒グラフ: いくつかの量を比べて、「どれが一番多いかな?」って見るときに使う。
- 折れ線グラフ: 時間とともに、どう変化しているかを見るときに使う。「増えてる!」「減ってる!」が一目でわかる!
- 円グラフ: 全体の中で、どれくらいの割合を占めているかを見るときに使う。「半分以上もある!」とか、「これはほんの少しだけ…」とか、パッと見てわかる!
- 帯グラフ: 割合の変化を見るときに使う。
- レーダーチャート: 複数の項目のバランスを比較するのに便利!
グラフ問題が出たら、まず、グラフのタイトル、縦軸と横軸の単位、凡例をチェック! これで、「このグラフは何を表しているのか」がわかります。
次に、一番大きいところ、一番小さいところ、大きく変化しているところに注目! 具体的な数字を読み取って、「A国の輸出額は、2000年から2020年にかけて、2倍以上も増えてる!」みたいに、自分の言葉で説明できるように練習しましょう。
さらに、「なんでこんなに増えたんだろう?」「この国で何があったんだろう?」って、グラフの背景にある理由まで考えられるようになったら、もう完璧!
伸びやすい教科は?:戦略
「地理って、覚えること多くて大変そう…」って思ってる人、いませんか? 実は、地理は、頑張れば頑張るほど、成績が伸びやすい教科なんです!
なぜなら、地理は、暗記する部分も多いけど、「なぜそうなるのか」という理由を理解することがとっても大切だから。例えば、「この国は、なんでこんなに暑いの?」「この地域は、なんでこんなに雨が多いの?」…みたいに、疑問を持つことが、地理の勉強の第一歩!
そして、その疑問を解決するために、教科書を読んだり、地図帳を見たり、資料集を調べたり…そうやって、自分で答えを見つけることが、地理の面白さなんです!
具体的な勉強方法としては、まず、教科書をしっかり読むこと。そして、重要な言葉や数字を、ノートにまとめること。さらに、一問一答問題集や過去問を繰り返し解いて、知識を定着させること。
地図帳は、いつも手元に置いて、パラパラめくる習慣をつけるのがおすすめ。眺めているだけでも、新しい発見があるかもしれませんよ!
そして、ニュースや新聞にも、ちょっとだけ目を向けてみましょう。世界のどこかで起こった出来事が、実は地理と深く関係している…なんてことは、よくある話です。「この国で紛争が起きたのは、資源が関係しているのかな?」「この地域で地震が起きたのは、プレートの動きと関係があるのかな?」…みたいに、ニュースを地理の視点から見てみると、より深く理解できるようになります。
地理は、暗記科目だと思われがちですが、実は、「考える力」も試される科目です。覚えた知識を使って、問題を解いたり、資料を読み解いたり、自分の意見を述べたり…。そうやって、「考える力」を鍛えることが、地理の成績アップにつながります。
「地理って、難しい…」って諦めないで! コツコツ努力すれば、必ず結果が出る教科です。頑張って!
高校受験で何年生の問題が多い?
「高校受験の地理って、何年生の内容が出るの…?」って、気になりますよね。実は、中学1年生から3年生までの内容が、全部出るんです!
でも、心配しないで! 中学1年生で習うのは、世界の地形や気候、日本の国土や都道府県など、地理の基礎の基礎。中学2年生では、世界の国々や日本の各地方の特色、産業などについて、もう少し詳しく学びます。そして、中学3年生になると、地球的課題(環境問題、資源問題、人口問題など)や国際協力など、より広い視野で地理を学ぶことになります。
つまり、どの学年の内容も、とっても大事ってこと! でも、特に、中学3年生で習う内容は、難しい問題が出やすいので、しっかり対策しておく必要があります。
高校受験対策としては、まず、中学1年生と2年生の内容をしっかり復習して、基礎を固めること。そして、中学3年生の内容を重点的に学習すること。これが、合格への近道です!
高校受験 地理 覚えること 知恵袋:Q&A
Q: 地図記号、たくさんあって覚えられない…! 何か良い方法ない?
A: 地図記号って、確かにたくさんあるけど、一つ一つをじっくり見てみると、意外と面白い形をしているものが多いんです。「お寺の記号って、お寺の屋根の形に似てる!」とか、「学校の記号って、文って字が入ってる!」みたいに、形と意味を結びつけて覚えると、楽しく覚えられますよ。自分でオリジナルの地図記号カードを作って、友達とクイズを出し合うのもおすすめです!
Q: 世界の国名と首都、覚えるのが大変すぎる…! コツってある?
A: 世界の国名と首都、全部覚えるのは、確かに大変…。でも、地域ごとにグループ分けして覚えると、意外とスムーズに頭に入ってきます。「アジアの国々」「ヨーロッパの国々」…みたいに、大きなグループに分けて、さらに「東アジア」「西アジア」…みたいに、小さなグループに分けていくと、覚えやすくなります。白地図に国名と首都を書き込む練習も、効果的ですよ!
Q: 統計データって、数字ばっかりで、つまらない…! どうすれば楽しく覚えられる?
A: 統計データは、丸暗記しようとするから、つまらなくなっちゃうんです。「なぜこの国は、この農産物の生産量が多いんだろう?」「なぜこの国は、この資源がたくさん取れるんだろう?」…みたいに、「なぜ?」を考えることが大切。理由がわかると、数字にも意味が出てきて、面白くなってきますよ。グラフや表を使って、視覚的に覚えるのもおすすめです!
おすすめ勉強法と総まとめ

まとめ
- 六大陸と三大洋、主要国の位置と首都は、地図帳で視覚的に覚えるのが基本
- 日本の都道府県と県庁所在地は、地方ごとにグループ分けし、白地図で練習する
- 農産物・鉱産資源の生産量上位国は、統計データと「なぜその国で多いか」の理由をセットで覚える
- 一問一答形式の問題集を活用し、スキマ時間に基礎知識を反復学習する
- 雨温図、統計グラフなど、資料のタイトル・軸・凡例を確認し、変化のポイントを読み取る
- 時差問題は、経度15度で1時間の時差が生じること、東経は進み、西経は遅れることを理解する
- 地形図の読図は、等高線の間隔で傾斜の急緩を判断し、地図記号と縮尺も確認する
- 地理は歴史・公民・理科との関連性が強く、他教科の知識と結びつけると理解が深まる
- 統計グラフは、棒・折れ線・円・帯グラフなどの種類と特徴を把握し、変化の理由を考察する
- 高校受験地理は中1~3年の内容が全て出題範囲であり、特に中3内容は発展的なので重点的に対策する
- 地図記号は絵と意味を関連付け、国名・首都は地域ごとにグループ化して覚えるのが効果的である
- ニュースや新聞で時事問題に触れ、地理的背景(民族、宗教、資源など)を意識する
これらのポイントを押さえれば、高校受験の地理はもう怖くありません! 基礎知識の定着から応用問題対策、さらには他教科との連携まで、この記事で紹介した学習法を実践すれば、地理が得点源になること間違いなし。さあ、今すぐ地図帳を開いて、地理の世界を探検し、志望校合格への確かな一歩を踏み出しましょう!

