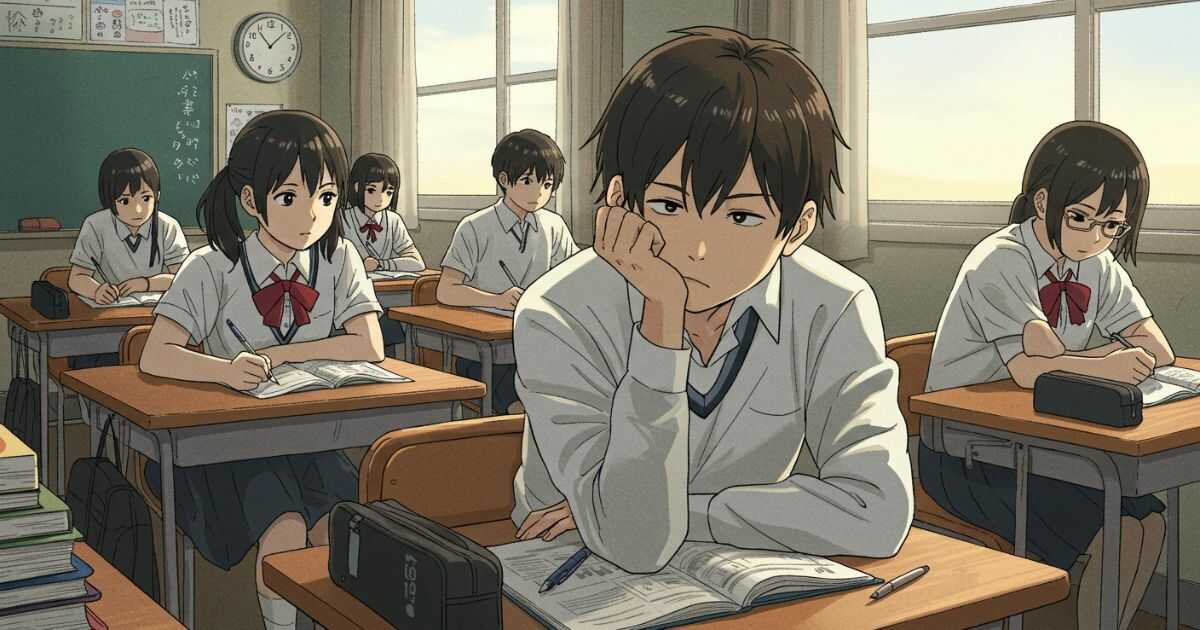「うちの子、塾に行ってるのに家で全然勉強しない…」「高いお金を払ってるのに意味あるのかな?いっそ塾をやめさせたい…」そんな風に悩んでいませんか?
中学生のお子さんを持つ親御さんなら、一度は抱えるかもしれないこの問題。この記事では、なぜ子どもが勉強しないのか、その心理や理由を探りながら、親として何ができるのか、後悔しない判断のためのヒントを一緒に考えていきます。
- なぜ勉強しないのか、根本原因を見極めることが第一歩です。
- 親の感情だけで判断せず、客観的な視点を持ちましょう。
- 塾を続ける・辞める以外の第3の選択肢も有効な場合があります。
- 親子で納得し、お子さんの将来につながる道を選びましょう。
勉強しない中学生に塾をやめさせたい、親の悩みに寄り添う対処法

この記事で分かること
- 中学生が塾に通っても勉強しない理由や心理状態
- ついやってしまいがち?勉強できない子へのNG対応
- 「塾をやめさせたい」と思った時の具体的なステップ
- 家庭学習やオンラインなど、塾以外の学習方法あれこれ
- 辞める?続ける?後悔しないための判断ポイント
多くの中学生が通う学習塾。でも、「塾で勉強しない」「宿題すらやらない」となると、親御さんの悩みは深まりますよね。月々の費用だって安くありません。「このまま通わせて意味があるの?」「思い切って塾をやめさせたい」そう感じるのは、決してあなただけではないはずです。特に受験が近づくと、焦りも出てきます。
ただ、すぐに行動を起こす前に、少し立ち止まって考えてみませんか?お子さんが塾で勉強しないのには、きっと理由があるはずです。「やる気がない」と一言で片付けず、その子の心の内を探ってみることが大切。授業についていけないのかもしれないし、他に夢中なことがあるのかもしれない。中学生という難しい時期の、親への反発心という可能性だってあります。ここでは、そんな親御さんの複雑な気持ちに寄り添いながら、解決の糸口を探っていきます。
親の焦りは当然です。でも、焦らない対応こそが、子どもの気持ちを開く第一歩なんですよ。
なぜ?中学生が塾に通っても勉強しない心理的背景
中学生が塾に通いながらも、家で勉強しなかったり、塾の授業に身が入らなかったり…。その裏には、いくつかの心理的な壁が存在することが多いです。一つ考えられるのは、勉強内容そのものへのつまずきです。「やっても分からない」「難しくて面白くない」と感じていると、どうしても意欲は湧きにくいもの。もしかしたら、小学校の内容から苦手が積み重なっているのかもしれませんね。
また、思春期ならではの心の動きも影響します。親や先生に「勉強しなさい」と言われると、かえって反発したくなる。そんな中学生特有の心理(心理的リアクタンス)が、「勉強しない」という行動につながっているケースも。あるいは、友達付き合いや部活、好きなことへの関心が強すぎて、勉強が後回しになっている可能性もあります。塾が勉強の場ではなく、友達との交流の場になっている、なんて声も実際に聞かれます。
そして、学ぶ意味が見いだせないというのも大きな壁です。なぜ勉強するのか、将来どう役立つのかがピンとこないと、なかなか本気にはなれません。知的好奇心や「分かりたい」という内側からの動機が育っていない、もしくは、親の期待がプレッシャーになりすぎて、かえって意欲を失っている…そんな可能性も考えられます。お子さんの心理を丁寧に読み解くことが、解決への第一歩になります。
親が「塾をやめさせたい」と感じる切実な理由とは
では、親御さんが「塾をやめさせたい」と強く思うのは、どんな時でしょうか。やはり一番大きな理由は、費用に見合う効果を感じられないことかもしれません。文部科学省の「令和3年度 子供の学習費調査」 によると、公立中学生の通塾者平均年間費用は約35.6万円(※)。決して安くない投資をしているのに、成績が上がらない、勉強しない姿を見ると、「もったいない」と感じてしまうのは当然です。
(※出典: 文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」
お子さんの将来に対する漠然とした不安も、親御さんを悩ませます。「このまま勉強しないで高校受験は大丈夫?」「将来、困るんじゃないか…」そんな心配が、「今の塾は意味がないのでは?」という結論に結びつきやすいのです。家で宿題もせず、スマホやゲームに夢中な姿を見ていると、ついイライラしてしまう…そんな経験はありませんか?
「子どものために」という気持ちと同時に、親自身の心の安定を求めている部分もあるかもしれません。「塾に行かせている」ことで少し安心していたのに、その効果がないと分かると、状況を変えたい(=やめさせたい)という気持ちが強くなることも。これらの切実な理由が重なって、「塾をやめさせる」という選択肢が現実味を帯びてくるのです。
中学生が勉強しない本当の理由、塾をやめさせたい親の焦りと葛藤

中学生のお子さんが勉強しない…。親としては、「なんで?」「このままで大丈夫?」と焦りや不安を感じますよね。そして、「これ以上お金をかけても…塾をやめさせたい」という考えが頭をよぎることもあるでしょう。でも、その決断をする前に、もう一度「なぜ勉強しないのか」その本当の理由を探ってみませんか?
もしかしたら、それは単なる怠けや反抗期ではなく、お子さんなりのSOSサインかもしれません。勉強のやり方が分からない、塾のレベルが合わない、他に悩みがある…。あるいは、「勉強しないのに塾には行きたがる」なんて、一見矛盾した行動にも、ちゃんと子どもの気持ちが隠されています。原因を見誤ると、せっかくの対応も空回りしかねません。ここでは、勉強しない中学生が抱える問題の核心と、塾をやめさせたい親御さんの葛藤の背景にあるものを見ていきましょう。
“勉強しない”という行動の裏にある“本当の声”に、まずは耳を傾けてみてください。
中学生が勉強できない、またはしない子の共通点
「うちの子、どうして勉強しないんだろう…」そう悩む中学生には、いくつか共通して見られる特徴があるようです。まず、「何のために勉強するのか」という目的意識が希薄なこと。将来の夢や目標がまだ漠然としていて、勉強の必要性を実感できていない子が多いですね。ゲームや友達との時間など、今楽しいことを優先しがちです。
次に、基礎的な学力が追いついていないケース。小学校や中学の早い段階でのつまずきをそのままにしてしまい、今の授業内容が理解できない。「やっても分からない」という経験が重なると、苦手意識がどんどん強くなってしまいます。
勉強のやり方自体を知らない、という子も少なくありません。計画の立て方が分からない、集中力が続かない、ノートをきれいに取るだけで満足してしまう…など。自分の学習を客観的に見て、やり方を工夫する力(メタ認知)がまだ育っていないのですね。
心の問題も影響します。「どうせ自分なんて…」という自己肯定感の低さや、失敗を恐れる気持ち、親や先生への反発心などが、勉強への壁になっていることも。中には、発達障害(ADHDやLD)の特性が関係している可能性もありますので、気になる場合は専門機関への相談も視野に入れましょう。生活リズムの乱れや、落ち着いて勉強できる環境がない、といった要因も無視できません。
勉強しないのに塾に行きたがる子どもの複雑な心理
家では勉強しないのに、「塾には行きたい!」と言う中学生。親としては「どうして?」と不思議に思いますよね。でも、これには子どもなりの、ちょっと複雑な気持ちが隠れていることが多いんです。
一番よく聞かれるのが、友達関係です。「仲良しの〇〇ちゃんが行くから」「行かないと仲間外れにされそうで…」など、塾が勉強の場というより、友達との大切な交流の場になっているケース。塾帰りのコンビニが楽しみ、なんて話も耳にします。
塾という場所に所属している安心感を求めている子もいます。たとえ勉強に身が入らなくても、「自分は塾に通っている」という事実が、漠然とした安心感や、「やるべきことをやっている(ふりだけでも)」という感覚を与えているのかもしれません。「親をがっかりさせたくない」「怒られたくない」という気持ちから、イヤイヤながらも通い続けている可能性もあります。
あるいは、家で「勉強しなさい!」と言われるのが嫌で、家から逃げるための口実として塾を利用している、という見方もできます。塾にいる間は、少なくとも直接的なプレッシャーからは解放されますからね。
自分で勉強の計画を立てたり、コツコツ努力したりするのが苦手で、塾というシステムに頼りたい、という気持ちも考えられます。「塾に行けば何とかなるかも」という、他力本願な期待を持っている子もいるでしょう。このように、勉強しないのに塾に行きたがる背景には、成績アップ以外の様々な子どものニーズが隠れていることを、まずは理解してあげたいですね。
塾に行っているのに勉強しない姿を見ると、ついイライラしてしまいます…。どう対応すればいいですか?
その感情、よく分かります。大切なのは、イライラをぶつけるのではなく、『なぜそうなっているのか』を一緒に探ろうとする姿勢です。否定ではなく対話を意識することで、子どもの心に届く言葉に変わっていきますよ。
塾をやめさせたい時の対応は?勉強しない中学生への親の接し方

お子さんが勉強しない。「もう、塾をやめさせたい!」その気持ち、痛いほど分かります。でも、感情に任せて「やめなさい!」と突き放してしまうのは、ちょっと待ってください。それは親子関係にも、お子さんのやる気にも、マイナスの影響を与えかねません。
かといって、成果が出ないまま高いお金を払い続けるのも辛いですよね。大切なのは、冷静に、そして建設的にアプローチすること。まずはお子さんとしっかり向き合い、本音を聞く。そして親の考えも伝え、一緒に「これからどうするか」を考える。そんな姿勢がカギになります。ここでは、勉強しない中学生に対して親ができること、塾をやめさせる場合の注意点、そして塾以外の選択肢について、具体的な方法を見ていきましょう。
勉強しない中学生の親にできる具体的なサポート方法
「勉強しない中学生に、親として何ができるの?」そう悩んだ時、試してほしいサポート方法がいくつかあります。「勉強しなさい!」と一方的に言うのではなく、お子さんの気持ちに寄り添うことから始めましょう。
まず、話を聞く姿勢を持つこと。「どうしてやる気が出ないのかな?」「何か困ってることある?」と、否定せずに耳を傾けてみてください。「大変だね」「その気持ち分かるよ」と共感するだけでも、お子さんは少し安心できるはずです。
次に、勉強しやすい環境づくりです。集中できる静かな場所を用意したり、スマホやゲームの時間を一緒に決めたりするのも良いですね。十分な睡眠や栄養バランスの取れた食事といった、基本的な生活習慣を整えることも、実はとても大切です。
具体的な学習面では、小さな目標設定を手伝ってみましょう。「今日は英単語を10個だけ」「問題集を1ページ」など、クリアできそうな目標を一緒に立て、できたら「頑張ったね!」と具体的に褒めてあげる。この「できた!」という小さな成功体験が、次への意欲につながります。結果だけでなく、努力の過程を認める言葉がけを意識したいですね。
お子さんの興味関心と勉強を結びつける工夫も効果的です。「このアニメの歴史背景って…」「将来〇〇になるには、どんな勉強が必要かな?」など、学ぶことの面白さや意味を一緒に見つけていく。そんな関わり方が、お子さんの内側からのやる気を引き出すきっかけになるかもしれません。ただし、管理しすぎは禁物。中学生には、自分で考えて決める力も必要です。「見守っているよ」というスタンスで、そっと背中を押してあげましょう。
お子さんとの関わり方、特に理解が難しいと感じる思春期の息子さんとのコミュニケーションに悩んでいるなら、その特性を知るヒントを与えてくれる本を読んでみるのもおすすめです。
そこでおすすめなのが、【まんがでわかる! 息子のトリセツ】です。
男性脳の専門家が、息子さんの行動や言葉の背景にある脳の仕組みを、マンガで分かりやすく解説しています。「なぜ言うことを聞かないの?」「どうしてそうなの?」といった疑問が解消され、具体的な接し方のヒントが見つかると評判です。
▶ レビュー高評価!息子さんとの関係改善のきっかけになるかもしれません。
無理やり塾を辞めさせる影響と親子関係の注意点
親御さんとしては、「効果がないなら塾をやめさせたい」と思うかもしれません。ですが、お子さんの気持ちを無視して、一方的に辞めさせてしまうことには、大きなリスクが伴います。
一番心配なのは、お子さんのやる気がますます失われてしまうこと、そして親子関係が悪化することです。たとえ勉強しないように見えても、お子さんなりに塾に意味(友達がいる、安心できる場所など)を見出している場合があります。それを頭ごなしに否定されると、「親は自分の気持ちを分かってくれない」と心を閉ざしてしまいかねません。反発心が強まり、勉強どころか、他のことへの意欲まで失ってしまう可能性だってあります。
また、「塾をやめたら、家で勉強するだろう」という期待は、残念ながら外れることが多いです。「塾」という最低限の学習機会やリズムがなくなることで、全く勉強しなくなるリスクも考えなくてはなりません。特に、自分で計画を立てて勉強するのが苦手な中学生の場合、塾の強制力がなくなった途端、学習習慣が完全に崩れてしまうことも。
もちろん、お子さんの心や体に深刻な影響が出ている、経済的にどうしても継続が難しい、といった場合は別です。しかし、そうでない限りは、まずお子さんとしっかり話し合うことが何よりも大切。「私はこう心配しているんだ」と親の気持ちを伝えつつ、お子さんの意見にも真剣に耳を傾ける。一方的な決定は避け、お子さんの「自分で決めたい」という気持ちを尊重する姿勢が、信頼関係を保ち、お子さんの成長を促す上でとても重要になります。
辞めさせること自体が“悪”ではありません。でも、“どう辞めるか”が親子関係を左右します。
家庭学習など塾以外の選択肢、代替手段の探し方
「塾をやめさせたいけど、勉強は続けてほしい…」そんな時、塾以外の学習方法に目を向けてみましょう。今は本当に色々な選択肢があります。お子さんの個性やペース、家庭の状況に合わせて、最適な方法を探すことが大切です。
まず考えられるのは「家庭学習」。教科書やワーク、市販の問題集を使います。自分のペースででき、費用も抑えられますが、計画性と自己管理能力がカギ。勉強しない傾向のある中学生には、親御さんのサポート(計画を一緒に立てる、時間を決めるなど)が必要になるでしょう。
最近人気の「オンライン学習・映像授業」。有名講師の授業を手軽に受けられ、時間や場所に縛られないのが魅力です。AIが苦手な問題を分析してくれるサービスも。ただ、これも自主性が求められます。ボーッと画面を見ているだけでは効果は薄いかもしれません。
昔ながらの「通信教育」。教材が届き、添削指導があるのが特徴です。学習管理のサポートが手厚いものもありますが、教材を溜め込まない工夫が必要です。
「家庭教師」は、マンツーマンでじっくり教えてもらえるのが最大の利点。苦手克服や、集団が苦手な子に向いています。ただし、費用は他の方法より高くなる傾向があります。
これらの選択肢を探す時は、まずお子さんと一緒に情報収集を。「体験してみる?」「これならやれそう?」と、本人の意見を聞きながら進めることが大切です。資料請求や無料体験を積極的に活用しましょう。「塾を辞めること」が目的ではなく、お子さんが前向きに学習に取り組める新しい道を見つけることがゴールです。
塾をやめさせたい決断の前に。勉強しない中学生のケーススタディ

「もう限界!うちの子も塾をやめさせたい…」そう決断する前に、少しだけ立ち止まってみませんか?他のご家庭ではどうしているのか、塾を辞めた、あるいは続けた結果どうなったのか、具体的な事例を知ることで、冷静な判断ができるかもしれません。
もちろん、どのご家庭にも、どのお子さんにも当てはまる「正解」はありません。しかし、様々なケースを知ることで、ご自身の状況を客観的に見つめ直す良い機会になります。ここでは、中学生が塾を辞める理由のデータや、実際のケーススタディ、そして少しシビアな視点ですが、塾側が「辞めてほしい生徒」についてどう考えているのか、といった情報をご紹介します。勉強しないお子さんへの対応に悩むあなたの、次の一歩のヒントになれば幸いです。
中学生が塾を辞める主な理由ランキングとその背景
中学生が塾を辞める時、その理由は何なのでしょうか?いくつかの調査(例: じゅけラボ予備校調査2023年など)を見てみると、共通する理由が浮かび上がってきます。学年によっても傾向は変わるようですが、よく聞かれる退塾理由は次のようなものです。
- お金の問題(費用対効果): 「月謝が高い割に成績が上がらない」「家計的に厳しい」というのは、特に中1・中2で多い理由です。目に見える成果がないと、投資を続けることに疑問を感じるのは自然ですよね。
- 時間がない・忙しい: 「部活や他の習い事と両立できない」「通塾に時間がかかる」というのも定番の理由。中学生は勉強以外にもやることがたくさんあります。
- 本人のやる気・塾嫌い: 「子どもが行きたがらなくなった」「授業がつまらない」など、本人の気持ちが直接の原因になることも。
- 家で勉強する方が良い: 特に受験を控えた中3になると、「家で自分のペースでやった方が効率的」という理由が増える傾向が。これは、塾への不満の裏返しかもしれませんし、自己学習への意欲の表れとも取れます。
- 塾との相性: 「先生と合わない」「授業のレベルが合わない」「クラスの雰囲気が苦手」といったミスマッチも、常に上位に挙がる理由です。
これらの理由の裏には、「勉強しない」という問題だけでなく、お子さんの性格や発達段階、家庭の状況などが複雑に影響しています。親が「やめさせたい」と思う理由と、お子さん自身が辞めたい理由は違うこともある、という点を覚えておきましょう。
事例から学ぶ、塾を辞めた/続けた判断の分かれ道
「塾をやめさせたい」「いや、続けさせるべき?」…判断に迷った時、他のご家庭の「その後」は気になりますよね。いくつか事例を見てみましょう。ただし、あくまで一例。ご自身のお子さんに当てはまるかは慎重に考えてください。
【良い方向へ向かった事例】
- 転塾でやる気アップ: 集団塾で勉強しない状態だった子が、基礎から丁寧に教えてくれる補習塾や、相性の良い先生がいる個別指導塾に移ったことで、意欲を取り戻したケース。
- 目標変更で前向きに: 親子で話し合い、中学受験から高校受験へ目標を変え、進学塾を辞めた。プレッシャーから解放され、本人がスッキリしたケース。
- 本人の成長を待つ: 一時期モチベーションが低かったものの、塾の友達や先生との関わりの中で、あるいは学年が上がり意識が変わって、自ら勉強に向かうようになったケース。
【難しい結果になった事例】
- 原因放置で悪循環: 学習習慣がない、基礎が抜けている、といった根本原因に向き合わず、「成績が上がらないから」と親が次々塾を変えた結果、どこにも馴染めず、かえって学力が低下したケース。
- 計画なく辞めて失速: 「塾さえ辞めれば…」と安易に辞めさせたものの、代替の学習計画がなく、全く勉強しなくなり、成績が急降下したケース。
これらの事例を見ると、うまくいくかどうかは、「辞めるか続けるか」という選択そのものよりも、「なぜ勉強しないのか」という根本原因を親子で(時には塾とも)共有し、その子に合った具体的な次の一手を打てるかどうかにかかっているようです。親の焦りだけで動くのではなく、お子さんの気持ちと状況をしっかり見つめることが大切ですね。
塾側が「辞めてほしい」と感じる生徒の特徴とは?
少し聞きにくい話かもしれませんが、塾側にも「正直、この生徒さんには困っている」「できれば辞めてほしい…」と感じてしまうことがあるようです。これは、お子さんが「勉強しない」から、という単純な理由だけではありません。塾も多くの生徒を預かる場であり、教室全体の環境や他の生徒への影響を考えなければならないからです。親が「塾をやめさせたい」と悩むのとは違う、塾側の視点も知っておくと、無用なトラブルを避けられるかもしれません。
塾が対応に苦慮しやすい、あるいは「辞めてほしい」と感じてしまいがちな生徒さんの特徴には、次のようなものがあると言われます。
- やる気の欠如と非協力的な態度: 宿題を全くしない、授業に参加しない、注意しても改善が見られない。これは指導以前の問題で、塾も限界を感じてしまいます。
- 授業妨害・迷惑行為: 騒いだり、他の子の邪魔をしたりして、教室全体の学習環境を乱してしまう。
- 遅刻・欠席の常習化: 学習リズムが作れないだけでなく、周りのモチベーションにも影響します。
- 保護者との連携困難: 塾の方針に協力的でない、連絡が取れない、過度な要求をするなど。信頼関係が築けないと、お子さんへの効果的なアプローチも難しくなります。
- 月謝の未払い: これは当然ながら、サービス継続の前提に関わります。
もちろん、塾はすぐに生徒を見放すわけではありません。面談をしたり、指導を工夫したりと、何とかしようと努力します。でも、どうしても改善が見られず、他の生徒や運営への支障が大きいと判断されると、最終的に退塾をお願いせざるを得ない、というケースもあるようです。勉強しない中学生だから即NG、というわけではありませんが、塾との良好な関係を保つ上でも、最低限のルールや態度は大切にしたいですね。
勉強しない中学生の将来は?塾をやめさせたい時の疑問とまとめ

目の前で勉強しない中学生のお子さんを見ていると、「この子の将来、一体どうなるんだろう…」と、言いようのない不安に駆られることがありますよね。ましてや、「もう塾をやめさせたい」と考えている時は、なおさらです。本当に辞めさせて後悔しない?他にできることはない?…尽きない疑問が頭を巡るかもしれません。
ここでは、そんな親御さんの疑問にQ&A形式でお答えしつつ、勉強しない中学生を安易に「ほっとく」ことのリスクにも触れていきます。そして最後に、これまでお話ししてきたことを踏まえ、親子で納得できる道筋を見つけるための大切な考え方をまとめます。
Q&A:塾や勉強に関するよくある質問と回答
塾の宿題を全くやりません。どうしたらいいですか?
まずは理由探しから。「難しい?」「時間がない?」「面倒くさい?」お子さんと冷静に話してみましょう。原因に合わせて、塾に量や難易度の相談をしたり、家でやる時間を決めたり、集中できる環境を作ったり。小さな「できた!」を褒めるのがポイントです。先生との連携も忘れずに。
勉強しないのに「塾に行きたい」と言います。なぜ?
まずは理由探しから。「難しい?」「時間がない?」「面倒くさい?」お子さんと冷静に話してみましょう。原因に合わせて、塾に量や難易度の相談をしたり、家でやる時間を決めたり、集中できる環境を作ったり。小さな「できた!」を褒めるのがポイントです。先生との連携も忘れずに。
親が無理やり塾を辞めさせてもいい?
基本的には避けたいところです。お子さんの気持ちを無視すると、反発心や不信感につながり、逆効果になることも。ただ、心身の不調や経済的な事情など、やむを得ない場合は別です。その場合も、必ずお子さんと話し合い、理由を丁寧に説明し、次のステップを一緒に考える姿勢が大切です。
塾に行っても成績が上がりません。辞めるべき?
成績が上がらない原因を探るのが先決です。塾の教え方?本人のやり方?基礎力不足?塾に相談して、クラス変更などの改善策がないか確認を。それでもダメなら転塾や退塾も選択肢ですが、家での学習習慣がない場合、塾を変えても同じことの繰り返しになる可能性も。原因への対処が先決です。
塾を辞めた後、どんな勉強方法がありますか?
教材を使った自宅学習が一番手軽ですが、計画性が重要。オンライン学習や通信教育も選択肢。家庭教師はマンツーマンで安心ですが費用がかかります。どれを選ぶにしても、お子さんの性格やペースに合うかが一番大切。一緒に体験してみるのがおすすめです。
まとめ:親子で納得できる道を見つけるために
まとめ
- 勉強しない中学生には多様な心理的背景がある
- 学習目的の欠如や基礎学力不足も一因
- 勉強しないのに塾に行きたがる子の本音を探る
- 親ができるのは叱咤ではなく共感と環境整備
- 小さな目標設定で成功体験を積ませるのが鍵
- 一方的に塾をやめさせるのはリスクを伴う
- 子どもの意見を尊重し対話することが不可欠
- 塾以外のオンライン学習や家庭教師も選択肢
- 他の家庭の事例から判断のヒントを得る
- 安易な放置は学力低下や無気力を招く恐れ
- 根本原因を見極め冷静に対応することが大切
- 長い目で子どもの成長を見守る姿勢を持つ
この記事のポイントを押さえれば、なぜお子さんが塾で勉強しないのか、その理由と親として取るべき適切な対処法が具体的に分かります。
感情的に「塾をやめさせたい」と考える前に、親子関係を悪化させず、お子さんの学習意欲を健やかに引き出すための関わり方や、塾以外の選択肢を含めた最適な道筋を見つけるヒントが得られるでしょう。後悔しないための冷静な判断力が身につきます。