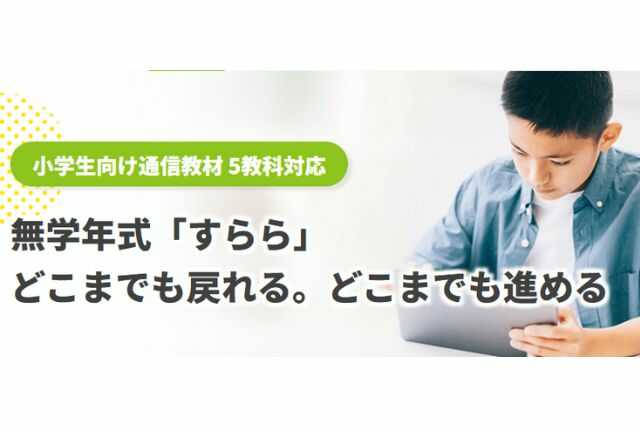「うちの子、どうしてこんなに勉強が苦手なんだろう…」「このままで、将来大丈夫かな」と、毎日不安な気持ちで過ごしていませんか?
特に、学校の授業についていけていないと担任の先生に言われたり、テストの点数が悪かったりすると、親として焦りや自己嫌悪に陥ってしまうものです。このまま一人で悩み続けないでください。
【忙しい方へ:要点まとめ】お子さんが勉強を苦手と感じる根本原因は、親の育て方や本人のやる気不足だけではありません。まずは「わからない」を「わかった!」に変えるための具体的なステップを知ることが大切です。家庭でのサポート方法を工夫し、子どもの「自己肯定感」を育むことができれば、きっと学習への意欲は引き出せます。この記事では、今日から実践できる解決策と、お子さんに合った学習ツールの選び方をご紹介します。
※この記事には一部PRが含まれます
勉強が苦手な子にイライラ…親が知るべき最初の3ステップ

勉強嫌いは克服できる!この記事でわかる解決への道筋
お子さんが勉強を苦手としている姿を見ると、ついつい「どうしてやらないの!」とイライラしてしまう気持ち、とてもよく分かります。しかし、ここで感情的になっても問題の解決にはつながりません。
まずは心を落ち着かせ、この記事で得られる知識を力に変えていきましょう。
この記事で分かること
- なぜ子どもが勉強を嫌いになるのか、その根本原因
- 子どもをやる気にさせるための親の魔法の声かけ
- 家庭でできる具体的な対策と行動のヒント
- 子どものタイプに合ったオンライン教材の見つけ方
「うちの子だけ?」その悩み、お一人ではありません
「周りの子はみんなちゃんとやっているのに、なぜうちの子だけ…」そう感じていませんか?
しかし、文部科学省の調査でも、多くの子どもが勉強に苦手意識を持っていることが分かっています。この悩みは、実は多くの親御さんが抱えている普遍的なものです。
東京大学とベネッセ教育総合研究所の共同調査(出典:https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0204_00002.html)によると、「勉強しようという気持ちがわかない」と回答した小中高生は、2019年の45.1%から2021年には54.3%へと増加しています。
このデータからも分かるように、お子さんの学習意欲低下は決して特別なことではありません。
| 項目 | 2019年 | 2021年 |
|---|---|---|
| 勉強しようという気持ちがわかない | 45.1% | 54.3% |
| 学校の授業がよくわからない | 28.5% | 31.8% |
| 授業がつまらない | 27.2% | 30.1% |
実は逆効果?「勉強しなさい!」が響かない理由
「勉強しなさい」という言葉は、親の愛情や不安の裏返しであることは間違いありません。
ですが、この言葉が子どもをさらに勉強から遠ざけてしまうことがあるのです。なぜなら、親からの一方的な命令は、子どもの「自律性」を奪い、勉強を「やらされるもの」に変えてしまうからです。
人は誰しも、「自分で決めて行動したい」という欲求を持っています。親からの指示ばかりでは、子どもは自分で考えることをやめてしまい、次第に「言われたからやる」「言われないならやらない」という受け身の姿勢になってしまいます。この状態では、どんなに素晴らしい教材を使っても、真の学習意欲は育ちません。
「私のせい?」と悩む前に知りたい、勉強嫌いになる本当の理由
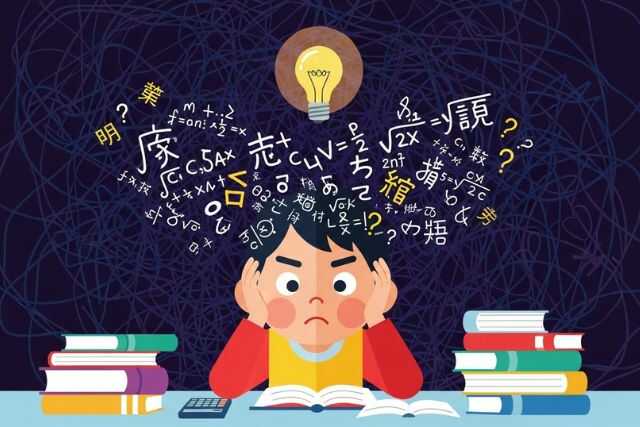
「わからない」が「やりたくない」に変わってしまう瞬間
もしかして、私の育て方が悪かったのかしら…。そう自問してしまう親御さんもいるかもしれません。
お子さんの「勉強が苦手」は、本当に「やる気がない」だけなのでしょうか?いいえ、その背景には「わからないから、できない」という根本的な問題が隠れていることがほとんどです。学校の授業は集団で進むため、一度つまずくと、その先の単元がすべて分からなくなってしまうという悪循環に陥りがちです。
この状態が続くと、子どもは「どうせやっても無駄だ」と感じ、失敗から自分を守るために「やりたくない」という態度をとるようになります。
親がこの悪循環に気づかず「やる気がないからだ」と叱ってしまうと、子どもはさらに心を閉ざしてしまうのです。
もしかして発達障害?家庭で見られる気になるサインとは
勉強の苦手さが、単なる「やる気」の問題ではなく、生まれつきの脳の特性に由来する発達障害である可能性も考慮する必要があります。例えば、何度教えても同じミスを繰り返したり、授業中にじっと座っていられなかったりする様子は、本人の努力不足ではないかもしれません。
以下のような様子が見られる場合は、専門機関への相談も視野に入れてみてください。
- 文字の読み書きが極端に苦手(文字がゆがんで見える、鏡文字になる)
- 計算の繰り上がりや繰り下がりがなかなか覚えられない
- じっと座っていられず、注意がそれやすい
- 忘れ物や失くし物が多い
- 特定の物事へのこだわりが強く、予定変更が苦手
自己肯定感の低下が学習意欲を奪う悪循環
勉強を頑張っても成績が上がらない、先生に当てられても答えられない、そんな失敗体験が続くと、子どもの心は深く傷ついてしまいます。
このような経験は「どうせ自分はダメだ」という自己肯定感の低下につながり、勉強に対する恐怖心を植え付けます。
すると、子どもは失敗を恐れて勉強から逃げるようになり、ますます学習機会を失っていくという悪循環が生まれてしまいます。逆に言えば、小さな成功体験を積み重ね、親が結果だけでなく努力を認めてあげることで、自己肯定感を育み、この悪循環を断ち切ることができるのです。
ゲームや動画が楽しいから?集中力が続かない子の心理
「スマホやゲームはあんなに集中できるのに、どうして勉強は続かないの?」と疑問に思ったことはありませんか?
これは、脳の「報酬系」が深く関わっています。ゲームは、すぐにクリアやレベルアップという短期的な快楽が得られますが、勉強は成果が出るまでに時間がかかります。
結果として、脳はすぐに報酬が得られるゲームを優先し、勉強を後回しにしてしまうのです。これは、子どもが怠けているわけではなく、脳の自然な反応でもあります。重要なのは、この脳のメカニズムを理解した上で、勉強を「楽しい」「できる」と感じさせる工夫をすることです。
勉強嫌いを克服!今日から家庭でできる5つのアプローチ

ステップ1:まずは学習環境の見直しから始めよう
色々試したけれど、どれもダメで…。そう感じている親御さんもいるかもしれません。お子さんが勉強に向かうための第一歩として、物理的な学習環境を整えることが大切です。勉強に集中できる空間が確保できれば、子どものやる気は自然と高まります。
以下のポイントを参考に、お子さんと一緒に環境を整えてみましょう。
- 静かな場所を選ぶ:テレビや漫画、ゲーム機から離れた静かなスペースを確保する。
- 整理整頓:勉強机の上は、今使うもの以外を置かないようにする。
- 時間を決める:「夕食後、まず15分だけ」など、短くても毎日決まった時間を設ける。
- タイマーを活用:ストップウォッチやタイマーを使い、時間を意識させる。
ステップ2:「勉強しなさい」を魔法の声かけに変えるコツ
感情的になって叱ってしまうと、子どもは勉強そのものに嫌なイメージを持ってしまいます。そこで、命令ではなく対話を意識した「魔法の声かけ」に切り替えてみましょう。
- 命令から問いかけへ:「勉強しなさい」→「今日の宿題は何がある?どこからやる?」
- 共感を示す:「勉強したくない」→「疲れてるんだね、その気持ち、よくわかるよ」
- 「私」を主語にする:「なんでやらないの?」→「お母さんはあなたが将来困らないか心配なの」
ステップ3:小さな「できた!」で自信を取り戻させる方法
勉強が苦手な子どもにとって、「できた!」という成功体験は最高の栄養です。テストの点数や結果だけを見るのではなく、努力の過程をしっかりと褒めてあげましょう。
- 具体的なプロセスを褒める:「すごいね!」→「昨日は解けなかった問題が解けたね!」「難しい問題に挑戦したね、粘り強く頑張ったね!」
- 100点満点を目指さない:まずは「1問でも解けた」「昨日より5分長く机に向かえた」という小さな変化を称賛する。
ステップ4:「ほっとく」は最終手段?そのメリットと危険性
何度言っても勉強しない子どもに、もう「ほっとく」しかないと諦めてしまう保護者の方もいるかもしれません。確かに、無用な親子喧嘩を避け、子どもが自ら必要性に気づくきっかけになるというメリットはあります。
しかし、その一方で学力の低下が深刻化し、取り返しがつかなくなる危険性も伴います。大切なのは、完全な放置ではなく、見守りながらもいつでもサポートできる姿勢を示すことです。「お母さんはいつもあなたの味方だよ」というメッセージを伝えることで、子どもは安心感を得られるでしょう。
ステップ5:子どもの個性に合わせた学習方法を見つける
集団塾のペースについていけなかったり、家庭教師に反発してしまったり、お子さんに合った学習方法が見つからずに苦労している方も多いのではないでしょうか。しかし、今はオンライン教材の進化によって、子どもの個性や学力に合わせた最適な学習法を選べる時代になりました。
特に、自分のペースで好きなところから学べる「無学年式」の教材や、AIが苦手を自動で発見してくれるツールなど、従来の学習方法では難しかった「個別最適化」が可能になっています。
わが子に合うのは?家庭学習を支えるおすすめサービス5選

オンライン教材を選ぶ際は、単に料金や知名度だけでなく、お子さんの「苦手の原因」と「性格」に合ったものを選ぶことが重要です。ここでは、特に勉強が苦手な子どもにおすすめできる5つのサービスを、その特徴と選び方のポイントを交えてご紹介します。
【すらら】つまずきの根本原因から解消する無学年式教材
「勉強が苦手でも、わかるを積み上げやすい」と評価の高い無学年式オンライン教材です。
キャラクターと対話しながら進めるアニメーション授業は、ゲーム感覚で学習でき、飽きっぽいお子さんでも続けやすい設計です。さらに、発達障害の専門機関と共同開発されており、算数のつまずきを基礎から丁寧に解消できます。
- 苦手単元までさかのぼれる無学年式×対話型レクチャー
- 専門機関監修+コーチ伴走で継続しやすい設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 月額8,228円(税込)※小学コース〈4教科〉4ヵ月継続割(通常8,800円) |
| 対象学年 | 小1〜小6 |
| 教科 | 国語・算数・理科・社会(理科・社会は小3〜) |
| 学習方式 | 完全無学年式(戻り・先取りに対応) |
| 授業スタイル | キャラクターと対話型のインタラクティブ講義 |
| サポート | すららコーチが学習設計・相談に対応 |
| 専門家監修 | 発達障害の専門機関「子どもの発達科学研究所」と共同開発(低学年コース等) |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
【RISU算数】算数に特化して苦手意識を克服したいなら
算数に特化した専用タブレット教材です。つまずきの原因をAIが自動で判断し、さかのぼり学習を促してくれるため、お子さんが一人で学習を進めやすいのが特徴です。また、子どもの学習速度に合わせて料金が変動するシステムもユニークです。
- 算数に特化し苦手を細分化して克服
- 学習速度に応じた復習配信で定着
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 基本料35,376円/年(税込)+利用料0〜月8,778円(税込)※学習速度に応じ変動 |
| 対象学年 | 年中〜小6 |
| 学習方式 | 無学年制×学習データに基づく個別出題(自動) |
| 端末 | 専用タブレット(解約後も復習用として利用可) |
| 料金構成 | 年額基本料+月次利用料(上限8,778円) |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
【スタディサプリ】圧倒的コスパで学習習慣をつけたい家庭へ
専用端末不要で始めやすく、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る映像授業サービスです。
授業時間が15分と短いため、集中力が続かないお子さんでも取り組みやすいのはうれしいポイントです。保護者向けの「まなレポ」機能で学習状況を把握できるため、見守りながらのサポートも可能です。
- 定額で小〜高の講座まで見放題
- 保護者の見守りがしやすい通知機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 月額2,178円(税込)※12ヵ月一括は月あたり1,815円 |
| 対象学年・教科 | 小1・2:国語・算数/小3〜6:国語・算数・理科・社会 |
| 学習スタイル | 映像授業+ドリル(15分目安) |
| 保護者機能 | 「まなレポ」で学習時間・正答率等を通知 |
| 無料体験 | 初回14日間無料体験あり |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
【進研ゼミ】教科書準拠で学校の授業をしっかりサポート
長年の実績を誇る通信教育サービスです。教科書に準拠したカリキュラムで、学校の授業や宿題に直結した学習ができます。自動採点機能に加え、「赤ペン先生」による丁寧な添削指導や、オンラインライブ授業も受けられるため、理解を深めながら効率的に学習を進めることができます。
- 教科書準拠で学校の授業・宿題に直結
- 添削×ライブ授業で理解を深めやすい
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 毎月払い:5,590円(税込)※小4・チャレンジタッチ |
| 対象 | 小学4年生(チャレンジタッチ) |
| 端末 | 専用タブレット(チャレンジパッド) |
| 添削指導 | 赤ペン先生の添削あり |
| ライブ授業 | オンラインライブ授業(追加受講費0円) |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
【オンライン家庭教師WAM】マンツーマンで丁寧な指導を希望するなら
1対1のオンライン授業で、お子さんの学習状況や性格に合わせた完全個別指導が受けられます。
独自のオンラインシステムを活用し、苦手の根本原因までさかのぼって丁寧に教えてくれるため、集団塾では質問ができなかったお子さんでも安心です。自宅から授業を受けられるため、送迎の手間がないのも魅力です。
- 苦手の原因をさかのぼって個別最適に指導
- 送迎不要で自宅から受講可能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 40分×月4回:小4〜小6 月額6,400円〜(税込) |
| 指導形態 | 講師1対1の双方向オンライン授業 |
| 学習方式 | 独自開発の授業システム/もどり学習に対応 |
| 対象学年 | 小学生(小1〜小6) |
| コース時間 | 40分(90分コースもあり) |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
勉強が苦手な子を持つ親御さんのよくある質問(FAQ)

Q1. 勉強しない子の将来や末路が心配です…
A1. お子さんの将来を案じる気持ち、とてもよく分かります。
しかし、勉強が苦手なことと、将来の幸せは必ずしも一致しません。大切なのは、学力だけでなく、好きなことや得意なことを見つけて、それを伸ばすことです。勉強を通じて培われる「目標に向かってやり抜く力」や「回復力(レジリエンス)」といった非認知能力は、人生を豊かにする上で非常に重要です。
勉強以外の面でもお子さんの強みを見つけ、それを尊重してあげてください。
Q2. 子どもの勉強は100%親の責任なのでしょうか?
A2. 多くの専門家は、子どもの学力は親の関与だけでは決まらないという見解で一致しています。
子どもの学習は、本人の特性、学校、そして家庭環境が複雑に影響し合うものです。「〇〇のせい」と自分を責める必要はありません。大切なのは、親がすべての責任を負うのではなく、子どもを「支配」するのではなく、信頼関係を築き、共に課題に取り組む「伴走者」になることです。
Q3. ご褒美で釣って勉強させるのは効果がありますか?
A3. 短期的な効果は期待できます。特に、勉強への抵抗感が強い初期段階では、「これが終わったらゲームを30分」といったご褒美が、行動を始めるきっかけになることは多いです。
ただし、これに頼りすぎると「ご褒美がないとやらない」という状態になり、学ぶこと自体の楽しさや達成感といった「内発的動機付け」が育ちにくくなります。あくまで補助的な手段として活用し、徐々に「努力したこと」そのものを褒める声かけに切り替えていきましょう。
Q4. 専門機関に相談した方がよいケースはありますか?
A4. 以下のようなサインが長期にわたって見られる場合は、専門機関への相談を検討することをおすすめします。
- 学校に行くのを嫌がる、登校を渋る
- 腹痛や頭痛など、身体的な不調を頻繁に訴える
- 「どうせ自分はダメだ」という発言が顕著になり、自己肯定感が極端に低い
- 親子関係が著しく悪化している
児童精神科や発達支援センター、スクールカウンセラーなど、専門家の力を借りることで、お子さんの特性を正しく理解し、適切な支援方法を見つけられる可能性が高まります。
まとめ:一人で抱え込まず、子どもの可能性を信じて伴走しよう

「どうすればいいか分からない」と途方に暮れていた気持ちが、少しでも楽になっていれば幸いです。
お子さんが勉強を苦手とする背景には、単純なやる気だけではない様々な理由があること、そして親御さんの適切な関わり方が何より大切であることがお分かりいただけたかと思います。
本記事で解説した「勉強嫌い克服」の重要ポイント
- 「わからない」が「やりたくない」に変わる悪循環を断つこと
- 「勉強しなさい」を魔法の声かけに変え、自主性を引き出すこと
- 小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を育むこと
- オンライン教材を活用し、子どもの個性と学力に合った学習法を見つけること
まずは無料体験から!親子で踏み出す小さな一歩
今回ご紹介したサービスの中には、無料体験や資料請求ができるものも多くあります。
まずは「これならうちの子に合いそう」と感じたサービスを一つ選んで、気軽に試してみることから始めてみませんか?それが、お子さんの学習に対する苦手意識を克服し、自信を取り戻すための第一歩になるはずです。