塾に通わずに大学受験を目指していると、「模試の受け方」が分からず、不安な気持ちになりますよね。
この記事では、個人での申し込みから成績の活用法まで、独学で頑張る方の悩みを解決する手順を具体的に解説します。これを読めば、きっと自信を持って模試に挑戦できます。
【はじめに結論】塾に通っていなくても、模試は個人で簡単に申し込めます。河合塾の「全統模試」や駿台の「駿台模試」など、大手予備校の公式サイトからアカウントを登録し、希望の模試を選ぶだけ。まずは自分の学力レベルに合った標準的な模試を選び、年間計画を立てて挑戦してみてはいかがでしょうか。この記事で、その全手順を詳しく解説していきます。
この記事で分かること
- 塾なし受験生が抱える模試の悩みと、その解決策
- 自分のレベルと目的に合った大学受験模試の選び方
- 個人で模試に申し込む具体的な手順と年間スケジュール
- 受けた模試の結果を最大限に活かす復習・分析方法
- 模試に関するよくある質問とその回答
塾なしでの模試の受け方、一人で悩んでいませんか?

部活動と勉強を両立させながら、独学で大学受験に挑む。その毎日は、本当にすごいことです。
しかし、周りの友達が塾に通っているのを見ると、「自分の勉強法は本当に正しいんだろうか…?」「全国のライバルと比べて、今どのくらいの位置にいるんだろう?」と、ふと不安が胸をよぎる瞬間があるのではないでしょうか。
特に「模試」は、塾に通っていれば当たり前のように案内が配られますが、独学だと情報収集から申し込み、そして結果の活用まで、すべて一人でこなさなければなりません。その一つ一つのステップで、どうすればいいか分からず立ち止まってしまう気持ち、痛いほどよく分かります。
申し込みから復習まで、やるべきことが明確になる
ここでは、数ある模試の中から自分に合ったものを選ぶ方法から、具体的な申し込み手順、そして最も重要な「受けた後の復習と活用法」まで、一連の流れを余すところなく解説します。
この記事を読み終える頃には、今抱えている「何をどうすればいいか分からない」というモヤモヤとした不安が、具体的な行動計画に変わっているはずです。
模試が独学者の学習を加速させる最強の味方になる
塾に通っていないからこそ、模試は学習を加速させる「最強の味方」になります。学校のテストだけでは決して測れない、全国規模での客観的な立ち位置を教えてくれる、たった一つの羅針盤だからです。
模試を戦略的に活用すれば、自分の弱点を正確に把握し、限られた勉強時間をどこに集中させるべきか、明確な指針を得ることができます。受けっぱなしにせず、一つ一つの模試を確実に力に変えていくこと。そのための具体的な方法を、ここからお伝えします。
不安を解消し、自信を持って第一歩を踏み出そう
新しいことに挑戦するのは、誰だって不安なものです。でも、正しいやり方さえ知れば、その不安は「自分にもできそうだ」という自信に変わります。
この記事は、独学で励む方が一人で悩まずに、自信を持って模試という大きな一歩を踏み出すためのガイドブックです。大丈夫、一つずつ手順を追っていけば、必ずできます。さあ、一緒に合格への道を切り拓きましょう。
「自分の実力、このままで平気?」塾なし受験生のリアルな悩み

部活帰りの電車の中、ふとスマホでライバルのことを検索しては、「塾なしで大学受験を目指す」と決めたものの、漠然とした不安が頭をよぎることはありませんか。その不安の正体は、自分の努力が正しい方向に向かっているのか、客観的な指標がないことにあるのかもしれません。
ここでは、多くの独学受験生が抱える、模試にまつわるリアルな悩みを深掘りしていきます。きっと、これを読んでいる方も「これ、自分のことだ」と感じる部分があるはずです。
周りは塾で対策…客観的な立ち位置がわからず焦る
学校の定期テストでは良い点が取れていても、それが全国のライバルたちの中でどれほどの価値を持つのか、想像するのは難しいですよね。友人たちが「この前の模試、難しかったよな」「塾で志望校判定が出た」なんて会話をしているのを聞くと、「自分だけが取り残されているんじゃないか」と、言いようのない焦りを感じることもあるでしょう。
この「客観的な立ち位置の不明確さ」こそ、塾に通わない受験生が最初にぶつかる大きな壁なのです。自分の実力を正しく知らないままでは、志望校との距離感も測れず、効果的な学習計画も立てようがありません。
どの模試をいつ受ける?情報がなくて計画が立てられない
いざ模試を受けようと決意しても、次に立ちはだかるのが「情報不足」の壁です。「河合塾 全統模試」「駿台全国模試」「東進 全国統一高校生テスト」…。検索すればたくさんの模試が出てきますが、どれが自分に合っているのか、判断するのは至難の業です。
「この模試は難関大向け?」「今の自分のレベルだと、どの模試を受けるのが標準的なの?」「そもそも、みんないつ頃に受けているんだろう?」こうした疑問を解決する情報が身近にないため、計画を立てる段階で挫折してしまいそうになるのです。
「受けっぱなし」で終わるかも…結果の活用法が不安
無事に模試を申し込み、受験できたとしても、本当の勝負はそこからです。返却された成績表を見て、A判定やE判定に一喜一憂するだけでは、貴重な時間とお金をかけた意味がありません。
「偏差値や判定以外に、どこを見ればいいの?」「間違えた問題を、どうやって次の勉強に活かせばいいんだろう?」という具体的な活用法が分からないと、せっかくの模試も「受けっぱなし」で終わってしまうかも…。この「結果を力に変えられないかもしれない」という不安も、独学受験生に共通する悩みと言えるでしょう。
まずはコレ!目的と学力レベルに合う模試の選び方
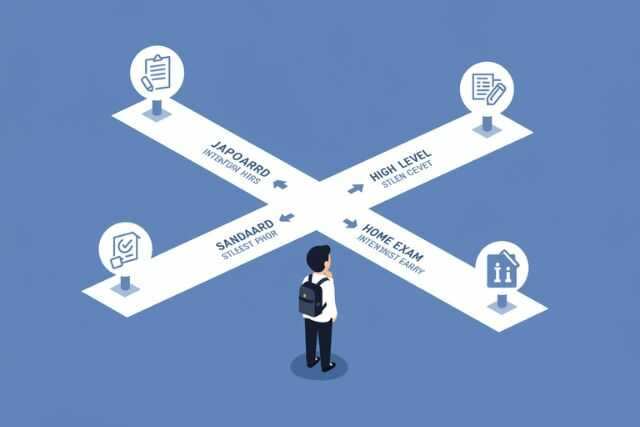
いざ模試を受けよう!と思っても、その種類の多さに圧倒されてしまいますよね。でも、心配はいりません。いくつかのポイントを押さえれば、誰でも戦略的に模試を選ぶことができます。
この章では、ご自身の目的と現在の学力レベルに合わせて、どの模試を選ぶべきかの指針を分かりやすく解説していきます。
【大学受験】主要3大模試の特徴とレベル感を徹底比較
大学受験模試は、主に大手予備校が主催しています。まずは、全国的に最も受験者数が多く、データの信頼性が高い「3大模試」の特徴を理解することから始めましょう。
| 予備校名 | 主な模試シリーズ | 特徴(レベル・母集団など) |
|---|---|---|
| 河合塾 | 全統模試 | 受験者数が国内最大級で、全国の標準的な立ち位置を知るのに最適。幅広い学力層が受験するため、データの信頼性が非常に高い。 |
| 駿台 | 駿台模試 | 難関大学や医学部を目指す受験生が多く集まるハイレベルな模試。最上位層の中での自分の実力を測りたい人向け。 |
| 東進 | 全国統一高校生テスト | 試験後、最短中5日で成績が返却されるスピード感が魅力。学習のPDCAサイクルを短期間で回したい場合に有効。 |
これらの特徴を参考に、今の自分の目的が「標準的な立ち位置の確認」なのか、「ハイレベルな挑戦」なのかを考えて選ぶのが第一歩です。
自分の現在地を知るための「標準レベル模試」とは?
では、もし「まず何を受ければいいか分からない」と途方に暮れているなら、最初に受けるべきは「標準レベル模試」です。具体的には、河合塾の「全統模試」などがこれにあたります。
なぜなら、このタイプの模試は受験者数が圧倒的に多く、様々な学力層の生徒が参加しているからです。そのため、算出される偏差値や合格判定の信頼性が高く、全国の受験生の中での自分の「現在地」を最も正確に把握することができます。まずはこの客観的なデータを得て、今後の学習計画の土台としましょう。
難関大志望者向け「ハイレベル模試」で実力を試そう
一方で、すでに基礎力に自信があり、東大・京大や医学部といった最難関大学を志望している場合には、「ハイレベル模試」に挑戦することをおすすめします。代表的なのは、駿台の「駿台全国模試」です。
この模試は、受験者のレベルが非常に高いため、同じ実力でも標準レベル模試より偏差値が低く出ることがあります。しかし、最難関レベルのライバルたちと競い合うことで、よりシビアな環境での自分の実力や課題が見えてきます。志望校のレベルに合わせて、戦略的に活用してみるのも一つの手です。
自宅受験と会場受験、どっちを選ぶ?メリット・注意点を解説
模試には、予備校や大学などの「会場」で受ける形式と、問題冊子を自宅に送ってもらい「自宅」で受ける形式があります。どちらを選ぶべきか、それぞれのメリットと注意点を理解しておきましょう。
- 会場受験のメリット・注意点
- メリット:本番さながらの緊張感を体験できる。時間配分の練習になる。
- 注意点:申込期間が短く、人気の会場はすぐに満員になることがある。
- 自宅受験のメリット・注意点
- メリット:自分の都合の良い時間に受けられる。部活などで忙しくても調整しやすい。
- 注意点:緊張感が保ちにくく、自己管理能力が問われる。
初めて模試を受けるなら、まずは本番の雰囲気を味わうために会場受験を経験しておくことがおすすめです。もし日程が合わなければ、自宅受験を活用する、という使い分けが良いでしょう。
塾なしで進める大学受験模試の年間計画と個人申込ステップ

自分に合う模試が見えてきたら、次は具体的なアクションプランです。「いつ、どの模試を受けるか」という年間計画と、「どうやって申し込むか」という手順。ここをしっかり固めれば、もう迷うことはありません。
ここでは、塾に通わなくてもスムーズに模試の計画と申し込みができるよう、具体的なステップを解説していきます。
高1・高2から始める!学年別の理想的な受験スケジュール
大学受験は長期戦です。行き当たりばったりで模試を受けるのではなく、年間を通した計画を立てることが、合格への道を着実に進むコツ。特に高2の時期は、ここからの1年半が非常に重要になります。
以下に、国公立大学志望者を想定した、標準的なスケジュールモデルをまとめました。
- 高2 春(4月~6月)
- 目的: 基礎力の定着度チェックと、自分のベースライン(出発点)の確認。
- 推奨模試: 河合塾「全統共通テスト模試」など、共通テスト形式の模試をまず1回。
- 高2 夏(7月~8月)
- 目的: 夏休みの学習成果の測定。
- 推奨模試: 共通テスト模試に加え、二次試験対策として「記述模試」にも挑戦してみましょう。
- 高2 秋〜冬(9月~1月)
- 目的: 志望校判定の本格化と、苦手分野の洗い出し。
- 推奨模試: 受験者数が最大規模になる秋の大規模模試(全統模試など)は必ず受けましょう。
- 高3
- 目的: 上記サイクルに加え、志望校の出題傾向に特化した「冠模試」も受験。
最低でも各学期に1回は模試を受けることを目標に、自分の学習進度に合わせて計画を立ててみてはいかがでしょうか。
カンタン4STEP!Webサイトからの個人申し込み完全ガイド
「個人で申し込むのは手続きが面倒そう…」と感じるかもしれませんが、実際は驚くほど簡単です。ほとんどの大手予備校の模試は、以下の4ステップで申し込みが完了します。
- STEP1:公式サイトでアカウントを作成
- 河合塾の「全統模試申込サイト」や、駿台の「I-SUM Club」など、各主催団体の公式サイトにアクセスし、メールアドレスや氏名、学校名などを登録して個人アカウント(マイページ)を作成します。
- STEP2:受験したい模試と会場(または自宅)を選択
- マイページにログインし、受験したい模試の一覧から希望の模試を選びます。次に、受験方式(公開会場 or 自宅)と、会場受験の場合は希望の会場を選択します。
- STEP3:受験料の支払い
- クレジットカード決済やコンビニエンスストアでの支払いなど、指定された方法で受験料を支払います。支払いをもって、正式に申し込み完了となります。
- STEP4:受験票のダウンロード・印刷
- 支払いが完了すると、マイページから受験票がダウンロードできるようになります。試験日までに自分で印刷し、当日会場に持参します。(自宅受験の場合は問題冊子が郵送されます)
各模試には申込期間が定められているので、受けたい模試が決まったら早めに公式サイトを確認する習慣をつけるのがおすすめです。
気になる費用はどれくらい?主要模試の受験料まとめ
模試を受けるにあたって、費用も気になるところですよね。塾に通っていない分、受験料は自分で管理する必要があります。
大学受験向けの有料模試は、1回あたりおおよそ6,000円から9,000円程度が相場となっています。例えば、2025年度に実施される河合塾の「全統模試」シリーズは、6,400円〜7,600円(税込)の価格帯で設定されています。
年間で複数回受験することを考えると、家計にとっても決して小さな負担ではありません。だからこそ、一回一回の模試を無駄にせず、最大限に活用することが大切なのです。
判定に一喜一憂しない!成績を次の成長に繋げる復習術

模試の結果が返ってくる日。期待と不安で、なんだかソワソワしてしまいますよね。でも、模試は受けて終わりではありません。むしろ、受けた後こそが最も重要です。返ってきた成績表のA判定やE判定という結果だけに心を揺さぶられるのではなく、その中身を深く分析し、次の学習への具体的なアクションに繋げること。
このプロセスこそが、自身の成績を飛躍的に伸ばす鍵となります。ここでは、そのための具体的な復習術を伝授します。
成績表で見るべきは判定より「弱点」!分析のコツを伝授
成績表が返ってきたら、まず合格可能性判定(A〜E判定)に目が行ってしまうのは自然なことです。しかし、本当に重要なのはそこではありません。ここで見るべきは、教科別・分野別の成績分析ページです。
そこには、「どの教科の、どの単元の、どの形式の問題で失点したのか」という、ご自身の弱点がデータとして克明に記されています。例えば、「数学は全体的に良いが、確率分野だけ正答率が低い」「英語は長文読解はできているが、文法問題でケアレスミスが多い」といった具体的な課題を発見できます。この「弱点の可視化」こそが、模試が提供してくれる最大の価値なのです。
自分だけの最強参考書に!「模試の復習ノート」作成法
発見した弱点を確実に克服するために、最も効果的なのが「復習ノート」の作成です。これは、単に間違えた問題を解き直すだけでなく、自分の思考プロセスや関連知識を集約した、「自分だけのオリジナル参考書」を作る作業だと考えてください。
例えば、数学の二次関数で間違えたなら、ノートにはその問題だけでなく、「解の公式、覚えてたつもりなのに!」「計算ミスが悔しい…」みたいな正直な心の声や、教科書の関連ページをメモしておく。そうすれば、世界に一冊だけの、自分の弱点を詰め込んだ最強の参考書が出来上がるんです。
| ノート作成のポイント | 具体的なアクション |
|---|---|
| 問題の選別 | 「間違えた問題」だけでなく、「正解したけど自信がなかった問題」もすべてピックアップする。 |
| 原因の分析 | なぜ間違えたのか?「知識不足」「計算ミス」「時間不足」など、ミスの原因を具体的に言語化して書き出す。 |
| 正しい解法の理解 | 解説を丸写しするのではなく、自分の言葉で「なぜその解法になるのか」を要約してまとめる。 |
| 関連知識の集約 | 間違えた問題に関連する公式や重要事項を、教科書や参考書で調べ直し、ノートに追記する。 |
このノートを定期的に見返すことで、知識は確実に定着し、同じミスを繰り返さなくなります。
次の模試で結果を出すための学習計画への反映方法
復習ノートで自分の弱点分野が明らかになったら、それを日々の学習計画に落とし込みましょう。例えば、「次の1ヶ月は、復習ノートで判明した数学の『確率』と英語の『文法』を重点的に強化する」といった具体的な目標を立てます。
- Plan(計画): 弱点分野の克服を学習計画の最優先事項にする。
- Do(実行): 計画に沿って、参考書や問題集で集中的に演習する。
- Check(評価): 次の模試で、その分野の成績が向上したかを確認する。
- Action(改善): 新たに見つかった課題に対し、再び計画を立てる。
このPDCAサイクルを回し続けることで、学習は「ただ何となくやる勉強」から、「目的を持った戦略的な勉強」へと進化し、成績は着実に向上していきます。
【初心者向け】塾なしでの模試に関するよくある質問と回答

ここまで模試の選び方から活用法まで解説してきましたが、まだ細かい疑問や不安が残っているかもしれませんね。この章では、塾なしで模試に挑戦する方が抱きがちな、よくある質問にお答えしていきます。
きっと、「これってどうなの?」という疑問も解消されるはずです。
Q. 塾に通わず模試だけ受けることは可能ですか?
A. はい、全く問題なく可能です。
これが最も多い質問の一つですが、心配は無用です。河合塾、駿台、東進といった大手予備校は、塾生でなくとも誰でも個人で申し込めるように、公式サイトを整備しています。
「塾に通っていないと受けられないのでは…」という心配は一切いりません。「模試だけ受けたい」というニーズは非常に一般的であり、そのための門戸は広く開かれています。安心して、公式サイトから申し込んでみてください。
Q. 中学生向けの無料模試にはどんなものがありますか?
A. 東進の「全国統一中学生テスト」などが代表的です。
大学受験は高校生だけの戦いではありません。中学生のうちから自分の学力を全国レベルで把握しておくことは、大きなアドバンテージになります。
東進が年2回実施している「全国統一中学生テスト」は、無料で受験できるにもかかわらず、詳細な成績分析が受けられる非常に価値の高い模試です。また、早稲田アカデミーなどが実施する学力診断テストも無料で受けられることが多いです。これらの機会を賢く活用し、早期から「模試慣れ」しておくことをおすすめします。
Q. 申し込みをキャンセルしたい場合はどうすればいい?
A. 主催団体によりますが、原則として「支払い後のキャンセル・返金」はできません。
一度申し込んで受験料を支払うと、自己都合でのキャンセルや返金は認められないケースがほとんどです。申し込む際は、部活の大会など、他の予定と重複していないか、事前によく確認しましょう。
ただし、受験料を支払う前であれば、支払期限を過ぎると自動的に申し込みがキャンセルされることが一般的です。もし間違えて申し込んでしまった場合は、支払いをせずに期限が過ぎるのを待つのが一つの方法です。
Q. 判定が悪くても落ち込む必要はないって本当?
A. 本当です。むしろ、悪い判定からこそ学ぶことが多いのです。
模試の結果、特にE判定のような厳しい結果を見ると、誰でも落ち込んでしまうものです。しかし、そこで自信をなくしてしまう必要は全くありません。
考えてみてください。本番の入試ではなく、今の段階で自分の弱点が見つかったのは、むしろ幸運なことです。模試はあくまで、今の実力を測り、合格までの課題を見つけるための「健康診断」のようなもの。結果は真摯に受け止めつつ、一喜一憂せずに「じゃあ、次は何をすべきか?」と前向きなエネルギーに変えることが何よりも大切です。
まずは自分の力を試してみませんか?河合塾や駿台の公式サイトで、直近の模試スケジュールを確認し、最初の一歩を踏み出してみましょう。
まとめ:塾なしでも大丈夫!模試を最高の羅針盤にしよう

ここまで、塾なしで模試を受けるための具体的な方法と考え方について、詳しく解説してきました。たくさんの情報がありましたが、一番伝えたいメッセージは「塾に通っていなくても、全く不利ではない」ということです。
むしろ、自分で情報を集め、計画を立て、模試というツールを戦略的に使いこなす経験は、受験勉強だけでなく、これからの人生においても大きな力になるはずです。
模試は君だけの戦略を立てるための最強ツールになる
模試は、受験生に3つの重要な価値を与えてくれます。
- 客観的な現在地: 全国のライバルの中での自分の立ち位置を教えてくれます。
- 明確な弱点: 次に何を勉強すればよいか、具体的な道筋を示してくれます。
- 貴重な本番経験: 入試本番で100%の力を発揮するための、最高の実戦練習になります。
これらの価値を最大限に引き出し、模試を自分だけの「合格戦略」を立てるための最強ツールとして活用してください。
不安になったらいつでもこの記事に戻ってきてください
独学での受験勉強は、時に孤独を感じ、不安になることもあるでしょう。そんな時は、いつでもこの記事に戻ってきてください。ここには、次の一歩を踏み出すためのヒントが詰まっています。
あなたの挑戦を、本当に、心から応援しています。この記事が、その努力を支える、信頼できる羅針盤の一つとなれば、これほど嬉しいことはありません。
